こんにちは。
今回はこんなテーマでやっていきます。
現在でも「村八分」なんて言葉はたまに使われますよね。そんな言葉はこの文化から生まれました。古き良き(?)日本文化を感じ取っていただいたら幸いです。
それではどうぞ。
目次
惣とは?
室町時代にできた自治的な村のことを言います。
できたきっかけは幕府の力が弱くなったこと。当時の情勢としては応仁の乱などで幕府の力が徐々になくなっていた時だったんです。
そんな中、村としても「幕府が守ってくれないなら自分たちでこの村を守らなくては」となり、自治的な村が多くなっていきました。
時代・読み方
室町時代のものです。
「そう」と読みます。
普段はあまり見慣れない文字ですよね。
構成人員
主に2つに分かれます。
の2人です。
いつの時代もどこの場所でもこういった身分の区別はありますよね。
主な組織
寄合(よりあい)
と呼ばれる会合がありました。今でいう町内会みたいな感じです。
これは先ほどのおとな(身分が高い人)しか参加ができないのですが、ここで村全体に関する重要なことが決められていました。
主な役割
結(ゆい)・もやい
村民がお互いに助け合うことを
と言いました。
惣掟
惣村内でのルールを惣掟といいます。
自検断
自分たちで警察の行為をおこなうことを自検断と言います。幕府はもう信用できなかったということですね。
地下請
村全体で年貢を払う=困ってる家があったら助け合うことを地下請といいました。
団結、そして一揆へ
村の人たちは団結をし、時に一揆という形で上の人たち(大体は守護)に反抗したりもしました。
一揆についてはこちら。
最後に
みんな苦戦する文化史の勉強法についてはこちら。
そして日本史の文化全体を幅広くまとめたおトクな記事はこちら。
今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。
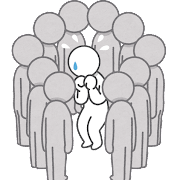


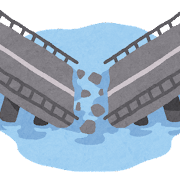



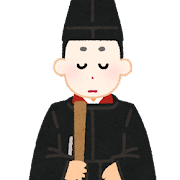
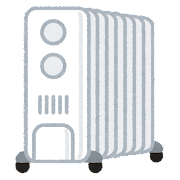
コメント