こんにちは。
今回はこんなテーマでやっていきます。
文化が始まるのは道徳では良しとされていないことからがほとんどですが、逆にそんなことだからこそ人々の心をつかみ、繁栄していくのかもしれません。今回はそんなお話です。
目次
阿国歌舞伎
歌舞伎はもともと出雲国の出雲阿国(いずものおくに)という女の人が作った舞踊です。なので阿国歌舞伎と呼ばれました。
しかしここで行われる踊りというのが女性がやっており、ちょっとアダルトなものだったので阿国歌舞伎は禁止されてしまうんです。そこでできたのが
若衆歌舞伎
です。
名前からして想像がつくと思いますが、今度は若い男の人を使って歌舞伎が行われて行きましたがこれも結局は江戸幕府によって中止にされてしまいます。
理由は男色。この時代では女性だけではなく若い男もアダルトの対象であり、それは決して珍しいことではありませんでした。
女もダメ。若い男でもダメ。ということでたどり着いたのが
野郎歌舞伎
です。
これはおじさんがやりました。野郎です。現在に近いスタイルですね。
ここで市川蝦(えび)蔵や坂田藤十郎といった名スターが生まれていきました。
ところで歌舞伎の名前は襲名制なので同じ名前を次の世代へ継いでいきます。市川海老蔵さんは今でもいますよね。
団菊左時代
明治時代に入ってからも歌舞伎は続いていきました。というか今でも続いていますよね。
そこで人気を博したのが
- 市川団十郎
- 尾上菊五郎
- 市川左団次
の3人。3人の名前の部分の足ら文字を取って「団菊左(だんきくさ)時代」と呼ばれました。
最後に
今回は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

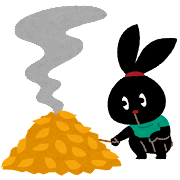





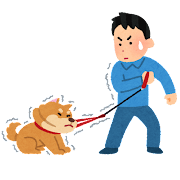
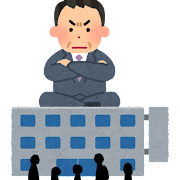
コメント